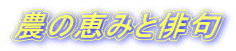
晩秋の茂吉の形ずいき芋 工藤博司
晩秋の茂吉の形ずいき芋 工藤博司
民報藤島2013年2月3日第881号
新つるおか2013年2月3日No.1827

昨年十一月、私達俳句の仲間は、上山市の斎藤茂吉記念館と、生家や茂吉が学んだ学舎などを訪ねた。斎藤茂吉は、第一歌集「赤光」によって、短歌会だけでなく、その後の日本文学にも多大な影響を与えた。
「死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞ゆる」「のど赤き玄鳥(つばくらめ)ふたつ屋梁(はり)にゐて足乳根(たらちね)の母は死にたまふなり」の歌は肉親の死を詠んで痛切極まりない。また戦後の歌集「白き山」には「しづかなる曇りのおくに雪のこる鳥海山の全(また)けきが見ゆ」「最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも」など山形県の山河を読んで秀抜である。しかし一方で、茂吉は「神ながらやまとだましひの攻撃や神風隊をさきがけとせる」などの聖戦歌も多い。詩人の評価は実作に即して厳密であらねばと思う。晩年の茂吉の姿は「ずいき芋」に似ていて、好々爺の思いがつよい。
(画・加藤貞雄)