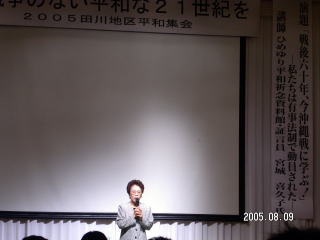2005田川地区平和集会「戦争のない平和な21世紀を」8月9日
 2005田川地区平和集会「戦争のない平和な21世紀を」が8月9日、東京第1ホテル鶴岡でひらかれました。
2005田川地区平和集会「戦争のない平和な21世紀を」が8月9日、東京第1ホテル鶴岡でひらかれました。
ビデオ「戦場ぬ童(いくさばぬわらし)」が放映され、元ひめゆり学徒隊の宮城喜久子さんの証言が1時間半、話されました。
沖縄が本土防衛の捨て石にされ、ひめゆり学徒隊として16歳の少女が戦場の地獄を90日間生きた語りは、聞いて胸につまりました。
おびただしい負傷者と死者の中で友人や先生が次々に死んでいき、奇跡的に命を取り留めた宮城さんですが、その地獄に向き合って語ることができるまで40年間が必要だったといいます。
宮城さんが証言を語るときは、その地獄を追体験することで、本人にとっていかにつらいことか察します。それでも証言者として語り続ける強い意志は、世界から戦争をなくしたいという強い決意です。
戦争を起こすのは時の政府であり政治権力です。いま政治家は2大政党制を競って平和憲法を改悪し、再び日本を戦争をする国にしようとしています。
さらに「先の大戦は正しい戦争だった」と子どもたちに教え込む歴史教科書を、学校現場に持ち込もうとしています。
「9条の会」に幅広く結集し、憲法を守り「戦争のない平和な21世紀を」築く政治権力を実現しなければなりません。
呼びかけ団体(教科書問題を考える市民の会・共立社鶴岡生協・庄内医療生協・I女性会議・田川地区高齢者退職者協議会・田川地区平和センター・鶴岡田川地域労連・原水爆禁止田川地区会議・原水爆禁止田川地区協議会・ピースウォーク鶴岡・日本共産党・社民党・新社会党)
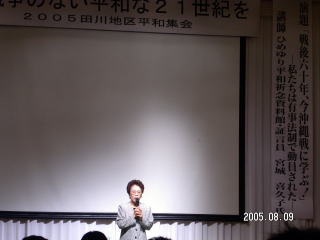
あの忌まわしい戦争のことは忘れよう、二度と思い出したくないと、あまり語ることをしなかった生存者が、一九八二年、ひめゆり平和祈念資科館建設が同窓会総会において決定したことを契機に、戦争体験を伝える活動を始めました。
その活動の中で、亡き学友の死を語ることの辛さを改めて感じながら、その死を無にしてはいけないという思いも深くなっていきました。
学友の写真をご遣族からいただく時、きまって聞く言葉 ── 「いま生きていたら……」の一言は、とても重いものでした。多くの同窓生の努力により、二一四名の遺影をひめゆり平和祈念資科館・第二展示室と第四展示室に安置できましたが、あと五名の姿はなく空白のままです。
やっと語ってもらった証言のテープ起こしも三十七年前の戦場に引き戻されるようで気が沈み、あるいはたかぶり、なかなか記録づくりは進みませんでした。
亡き学友の足跡をたどる中で、その死の様子があまりにもむごくて、知らない方がよかったと悔やむことも、しばしばでした。
資料館建設の活動がいかに厳しいものであるかを知りましたが、その活動の中から多くのことを学ぶこともできました。
資科館は、一九八九年六月二十三日に開館しました。九五年五月のいま、早くも六周年を迎えようとしています。この六年間に、四百万人余の方が全国からいらしてくださいました。その中の七十六万人余が、平和学習のために来館した小、中学生と高校生のみなさんです。
戦争のほんとうの姿を知り、あらためて命の尊さ、平和の大切さを汲みとったという感想を手にするとき、「知る」ことがどんなにだいじかということを痛感します。
戦中・戦後の長きにわたり私たちを導き、励ましてくださった仲宗根政善先生が、今年、一九九五年二月十四日、八十九歳の生涯を閉じられました。
戦争につながるいっさいのものを拒否し、ひたむきに命の尊さを訴えつづけられた先生のすばらしさは、多くの人の心の中に生きつづけることと思います。
「ぜひ出してください。平良松四郎先生をかこむ学友のことを、ぜひ正しく後世に伝えてください。亡き学友のために、亡き学友に代わって」
仲宗根先生からいただいた、何通かのお手紙の一節を引かせていただきました。
いま、やっと、亡き先生方、亡き学友のみなさんのことを本に残すことができました。 つたない私の記録ですが、人間にとってどんなに平和であることが大切か、戦争の時代を知らない若いみなさんがたが、ともに考え、語り合う一つのきっかけにしてくださることを心から願って(『ひめゆりの少女 十六歳の戦場』エピローグより)
リレートーク
ひめゆりの少女ーあれから60年
宮城喜久子(ひめゆり平和祈念資料館運営委員・証言員)
国策に沿う教育の申し子
あの当時の自分たちの姿を思い出すたびに、教育の力の恐ろしさを、まざまざと見る思いがしてなりません。
国策に反することを教える教師には、たとえそのことが正しい教えであろうと、厳しい処置が取られました。国は権力によって、教育の自由を侵害し、管理体制の下で教師をロボットのように動かしたいのです。個性のない、同じ型にはめられた人間づくりが、教師の手によって行われ、国策に沿う教育が着々と進められていったのでした。不幸にも、その教育の典型的な申し子が私たちだったのです。
敵に捕らわれることは、日本国民にとって恥辱の最たるものと教えられ、敵に捕らわれた女は、ひどい仕打ちをされると聞かされてきた私たちは、破局を迎えた戦場で、自分たちのとるべき道は自決すること以外はない、と誰もが思いました。そして、ついに、自分の手で自分の命を絶つ悲劇にまで追い込まれたのです。
うそで固められた教育を、そこまで信じ込まされたことに対して激しい憤りを感ぜずにはいられません。
あのいまわしい時代に遭遇したばかりに、尊い命を奪われた多くの学友の死を通してうったえたいことは、いつの世の戦いにも、犠牲を強いられるのは、若者達であり、国の体制によって国民を生かすことにも、殺すことにもなるということです。
死を逃れた命の重み
過ぎし日の戦いの恐怖が、昨日や今日のことのように生々しく思え、心の傷もいえぬまま、長い年月を過ごして来た沖縄県民の心を無視するかのように、基地は強化されているのが沖縄の現状です。やり場のない、心の底からの憤りを感じるのは私一人ではないはずです。沖縄県民が、幾度となく苦汁をなめてきたことは、これまでの長い歴史が物語っています。去る大戦において、沖縄が本土のための捨て石とされたこともその一つであることを、私たちは決して忘れてはいけません。
歴史は繰り返されると言われます。戦争に結びつく基地の存在を認めることが、またいつか来た道をたどることになるのは必至です。
国策の手段の教育からの解放
恐ろしい戦争の背景に誤った軍国主義教育があったことを、私たちは決して忘れてはいけません。人間の限りない未来を創造するためにあるはずの教育が、国策を進めるための手段として使われたとき、個人の尊厳は全く否定され、そこには人間としての教育は存在しませんでした。そして大切な平和も失われていったのです。管理体制の中で誤った教育を強いられ、苦悩した戦前の教師の姿を見て来た私たちは、教育の自由を侵害された教師がいかに悲惨であるかを知りました。そして二度とあのような過ちを繰り返してはいけないという、大きな教訓を得ました。物事を正しく見つめ、自主的に行動できる力を、一人ひとりの子どもが身につけ、伸び伸びと生きて欲しいと、心から願う日々です。今こそ、私たちが勇気と自信をもって、教育の自由を守り抜かなければならない時だと思います。
平和教育の原点は、教育の自由を守り、一人ひとりの子どもを大切にする真の人間教育の実践にあると言えるのではないでしょうか。 (みやぎ きくこ)

 2005田川地区平和集会「戦争のない平和な21世紀を」が8月9日、東京第1ホテル鶴岡でひらかれました。
2005田川地区平和集会「戦争のない平和な21世紀を」が8月9日、東京第1ホテル鶴岡でひらかれました。