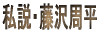
続・藤沢周平記念館を観る
企画展「蝉しぐれ」の世界① 青山 崇
『蝉しぐれ』に合って「しぐれ」に格別の情感を持つようになった。広辞苑を見てみる。時雨の表記だが、「過ぐる」から出た語で、通り雨の意とあり、①秋の末から冬の初め頃に、降ったりやんだりする雨で、すでに万葉集に見える。②比喩的に、涙を流すこと。③しきりに続くもののたとえ。「蝉しぐれ」などとある。また小督局(こごうのつぼね・高倉天皇の寵姫)の用いた琴や本阿弥光悦作の茶碗の名にも使われたという。豊富な意味を持ち名器の名にもなった優れた言葉である。ある解説者は「蝉しぐれ、というタイトルがよかった。」といい、それが眼を撃ち一夜にして読み終えたと書いている。
その名に恥じない名作を展示でどのように表現するのか、関係者の大変な努力が伺える。「『蝉しぐれ』が生まれるまで」とタイトルし、その創作過程を軸に、「物語をつづる」「挿絵の楽しみ」「創作の舞台裏」「庄内藩にみる海坂のおもかげ」「人々の心に残る『蝉しぐれ』」の順立てである。
もっとも印象深いのは、私の知見になかった「創作の舞台裏」で、その中でも「単行本化にあたって」である。あの名文「文四郎さんの御子が私の子で、私の子供が文四郎さんの御子であるような道はなかったのでしょうか」がある終章「蝉しぐれ」の大幅な加筆訂正で私にはいささか衝撃的であった。一箇所は、互いに子供の数など語った後「娘も、そろそろ嫁にやらねばなりません」という文四郎(助左衛門)の言葉以降である。二箇所は「これで思い残すことはありません」以降、終章の終わり、文四郎が失礼し砂丘を抜け「光の中に走り出」るところである。
