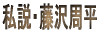
エッセイを読む
『ふるさとへ廻る六部は』⑫―世界に中心はない 青山 崇
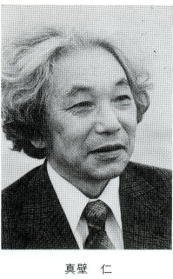 真壁仁はこのことをよく話した。「世界に中心はない。強いてあげたいなら自分の住む地域である。」というのだ。先号の言葉につづけて私見を述べよう。
真壁仁はこのことをよく話した。「世界に中心はない。強いてあげたいなら自分の住む地域である。」というのだ。先号の言葉につづけて私見を述べよう。
世界史教科書が大きく変わったことがある。コロンブスなどの世界探検の時代が「新大陸発見の時代」から「大航海時代」になったのである。すでに「発見」しインデアンなどの先住民族が住んでいたのである。それはヨーロッパから見た世界史であり、ヨーロッパ中心史観として排除されたのである。これを最初に指摘したのは、真壁が師と仰いだ上原専禄(歴史学者・元一橋大学長)だったと思う。
こう言われてみると、同じような史観が私たちの周りに常識化しているものがある。例えば工業中心史観や稲作中心史観がある。かつて先進国、後進国と世界の国を区別していたのを、後進国は差別として発展途上国に改めた。しかしいずれも工業中心史観での区別である。今世界は、ある価値観で国を区別するのでなく、異文明・異価値観の共存を歩む方向に向かっている。
稲作中心史観である。これは日本の古代史に現われたもので、稲作で弥生時代に発展したとし、稲作が行われない採集・狩猟中心の生活であった縄文時代の東北を遅れた地域とした。しかし、実際は西日本と同時に稲作を始めたのだが、東北はブナなどの広葉樹林に恵まれ、またサケ・マスが豊富に遡上し、採集・狩猟で生活ができたのである。それを無視し稲作の存否で歴史の進歩を決めるのは誤りであろう。

真壁仁はこのことをよく話した。「世界に中心はない。強いてあげたいなら自分の住む地域である。」というのだ。先号の言葉につづけて私見を述べよう。