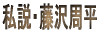
『春秋山伏記』⑧―野平村は生地・高坂をモデルか
青山 崇
注意して読むと、地形や風景から野平村は高坂のように思える。作品のなかからそう推測できる部分を取り出してみる。
村の鎮守は、大鷲坊を「櫛引通野平村、薬師神社の別当に任ずる。」「近くの薬師神社の森が、うす朱(あか)く染まっている。」「どーん、どーんと腹にひびくような太鼓の音が聞こえてくる。盆踊りの時に使う陽気な太鼓ではなく、薬師神社の神鼓である。」などとあって薬師神社である。赤川右岸の櫛引通に薬師神社はなく、その風景から高坂の薬師神社を思わせる。「別当の家は、神社の境内とは垣根ひとつへだてた場所にある。」とあり高坂の薬師神社の風景である。
「村の奥の山ぎはにある寺に、お参りにくる者などが、村に入ってくる。」という寺は、小菅家の檀那寺で周平の位牌がある洞春院である。三方が小高い山に囲まれ、池もあって静寂なやや高い平地で月山や野平村のある辺りが遠望できる。
「村の家々は、曲りくねって北に流れる小流れの西側にあるが、小流れの東にも三軒の家がある。」と村の家々の配置を書いている。青龍寺川を小流れにしているが、高坂の集落は、青龍寺川の西側にほとんどの家があり東北に数軒の家が点在している。小流れを除いてまったく同じである。なお黒川地区椿出のK家当主の祖母の実家は、周平生地から百メートルほど南にあるI家である。祖母は、周平は頭のいい子だといつも言っていたという。周平は高坂とこの地のかかわりを知っていて野平村をここに設定したようでもある。
ここにも周平の高坂への思い入れが見える。東京文化賞受賞のとき「いつも山形の方を向いている」私に資格があるのかと言ったという、その山形の中心に生地・高坂がいつも座っていたのである。
