
型付け(ワク) 佐藤治助
民報藤島2002年2月24日第331号
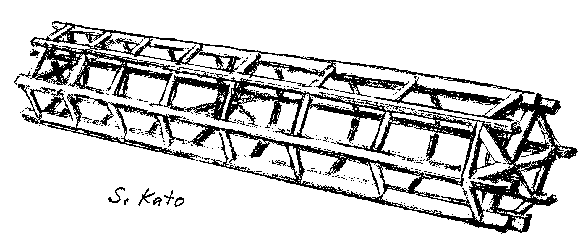
田植えのとき、苗の間隔をきちんとするため田に型をつける。その八角形の木で作った農具が「型付け」である。しかし、庄内ではワクといっていて、回す役はどの家も水戸守が引きうけていた。とうぜん、苗は縦横の線が交差するところに植えることになる。
私が百姓をはじめた一九三0年代後半(昭和10年〜)は、どこでもこのワクを使っていた。田圃はまだ耕地整理が完全でなく、四角な田ばかりではなかった。小さな丸い田や三角から菱形のものもあって、ワクを回せない所もあった。が、縄も張らず見当でうまく植えていたようだ。
村山方面では女が苗取り、男が植え役。庄内は反対で女がソドメショになって植えた。ワク回しは女には無理だから、とうぜん男の仕事だった。父にはじめて教えられたとき、右側の線に合わせるのがむずかしかった。とくに代掻きが悪く、あちこちデコボコの田はうまくいかなかった。コロリ、コロリと遅くなり、大勢雇衆がいるときなど、植え役を遊ばせることになって苦労した。しかし、村の中にはすいすいと風車のように回す達人もいて、うらやましかったものだ。
まだワクのなかった昔は縦の線だけ引くような、六つ七つの小さな木の車をつけた農具が使われていたのだろうか。物置小屋の隅に残っていたのを覚えている。
※編集部注・この辺りではワクはカタワク、水戸守は鍬頭(かがしら・農作業の責任者)と呼んでいた。