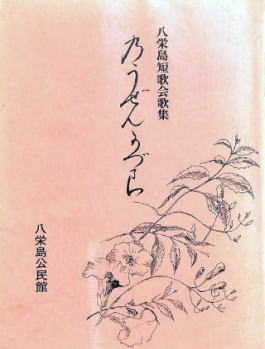
私たちの地区・八栄島は、俳聖芭蕉が「奥の細道」行脚以来、俳句や短歌が盛んになり、数多くの連句や短歌が残されている。
郷土の史跡に関心のある方にとっては、興味深いものもある。
手向村の出で芭蕉に弟子入りした呂丸(ろがん)の高弟・土田竹童(藤島・下町出身)がおり、その高弟であった海藤竹風は、八色木の海藤徳右衛門家生まれであった。
竹風は、近郷の歌人を集めて吟詠している。
その思想が八栄島地区に文人を生み出しているのではないか。
昭和44年(1969)、鈴木正治先生(松山町生まれ)が、八栄島小学校長として赴任され、校務の傍ら社会教育に心血を注がれ、特に短歌の指導をされていた。
質実剛健の方でスポーツも熱心であったし、西郷南州翁の解説もしていた。
2年後鶴岡市第二中学校長に栄転された。
歌集「半纏木」(はんてんぼく)を出版されたが、出版を待つかのように黄泉の旅に発たれた。
日向富さんが、先生の遺志を継いで、埋もれている作品を掘り起こし、歌集「のうぜんかづら」(凌霄花)としたのである。
のうぜんかづらは、八栄島小学校の校章で、真っ赤な花が真夏の空に向いて咲き誇るたくましい花である。
発刊に当たって、当時の公民館長鈴木重雄と、藤島図書館長阿部公彦が寄稿している。
どうか当時を懐かしんで読んで欲しいと思う。
昭和47年(1972)以降の会員27人の中から、順次掲載したい.
墓碑に刻まれた短歌
むらさきの煙にまごふ野に分けて
心わびしく吾は逝くなり 小鷹武治
桜花嵐に散りて日の本能
護団の霊となるぞうれし幾 斎藤四郎
鈴木正治先生遺作短歌
少年が白鳥を呼び川に撒ける茶殻の匂い風運 び来る 鈴木正治
第1回例会詠草 (昭和44・12・17)
賀状書く手もそぞろなりもの思い今年は如何 に君過ごさむや 石川重雄
老眼鏡は未だ早しと言ひつつも眉をしかめて 新聞を見る 石川錬太郎