『エミール』
学校統廃合を進める人たちは、子どもは、「少ない集団では社会性が育たない」と言いますが、そうでしょうか?
近代教育学のバイブルである名著、ルソーの『エミール』には、
「人間はあらゆる動物のなかで、群れをなして生活するのにいちばんふさわしくない動物だ。
羊の群れのようにひしめきあっている人間はすべて、たちまちのうちに滅びてしまうだろう。」(岩波文庫66頁)
と書いてあります。
『エミール』は1人の子どもをルソー自身があずかって、赤ん坊から青年期に至るまでの教育方法を論じました。
幼年期は、田舎で自然の中で育てる、
少年期は、自然観察や遊びを通じて、周囲の世界を理解する力を育てる、
青年期は、社会のルールや道徳的な判断力を養う、
「子どもを早くから集団に投げ込むべきではない」と批判したルソーに、学ぶべきではないでしょうか。
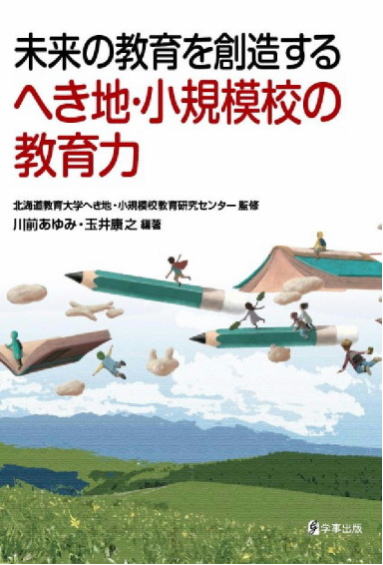
『未来の教育を創造する へき地・小規模校の教育力』北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター監修(学事出版2024.03.31)