藤島小、東栄小、渡前小と藤島中を統合し、小中一貫校とするものです。
人口減少・少子化が深刻な状況にある中、全国的には学校統廃合を進めるところと、逆に小規模だからこその充実した教育ができるとする地域に、分かれてきています。
藤島地域は重大な岐路に立っています。
少人数を逆手に
日本農業新聞元日号に、「地域に根差す小規模校〝草の根〟で守る 少人数を逆手に」の記事が大きく載り、注目されます(写真)。
岐阜県山県市(やまがたし)や和歌山県高野町(こうやちよう)、広島県三次市(みよしし)、高知県の県立中村高校西土佐分校(四万十市(しまんとし))の取り組みが紹介され、過疎化が進む中でも小規模校を残して地域の活性化を図り、成功している事例です。
協調性も自主性も
北海道教育大学の玉井康之教授は、「小規模校は『クラス替えができないので人間関係が固定化する』ともいわれますが、実は子どもの数が多くなればなるほど小グループ化して、特定の子どもとだけ付き合うことになります。
逆に、農村の小規模校では、少ない人数で多世代と濃密な人間関係で生活します。
各自の役割を与えられ、協調性も自主性も育まれます」と述べています。
同大学の『未来の教育を想像する へき地・小規模校の教育力』に学ぶ必要があります。
同書は小規模校の教育実践をまとめたもので、「個別最適な学びと協働的学び」を始めとした現代的な教育施策が、小規模校においてこそ進めやすい条件があるとされます。

日本農業新聞2025年1月1日付「地域に根差す小規模校」
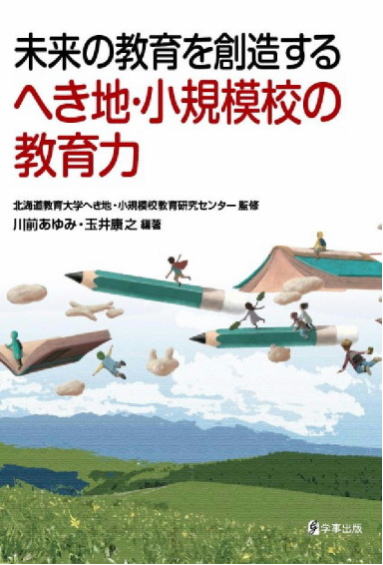
『未来の教育を創造する へき地・小規模校の教育力』北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター監修(学事出版2024.03.31)