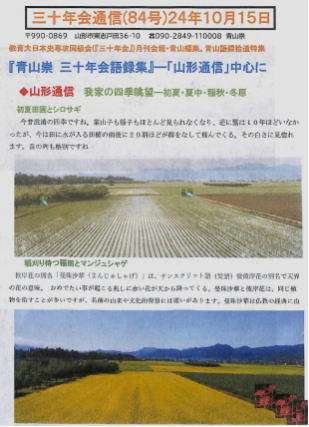前号の「マル共ハナ鰹(マルトモハナカツオ)」について、佐高信(さたか まこと)著『荘内人脈記 80通の思郷通信】(荘内日報社2018・7・1)にも載っていた。
「青山さんは私が庄内農高に赴任するのと入れかわりに山添高校に転出されたが、同じ社会科の教師として、あるいは組合が支援しない不当配転反対の闘いの仲間として交流があった。」
「当時、マルトモという会社の花鰹(鰹節を薄く削ったもの)が評判だった。トモは共で警察の隠語で共産党員を指し、中でも要注意人物に花丸をつけたので、それに引っ掛けたのである。」(186頁)
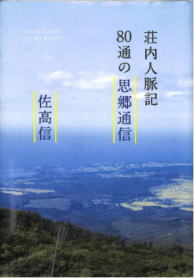
青山崇先生は1951年4月、東京教育大学文学部に入学し、同大学歴史学研究会に参加した。
石母田正『歴史と民族の発見ー歴史学の課題と方法』の「国民の中へ」の呼びかけに啓発され、活動を始めたことが、セツルメントとの出会いと述べている。
セツルメントとは、宗教家や学生などが、都市の貧困地区に宿泊しながら、授産所や託児所、その他の設備を設け、住民の生活向上のために助力する社会事業のことである。
先生は「30年会語録集」に、「人生の原点」として、「人生を広げ深めてくれたセツルメント」と書いている。
先生は退職後、「農民の中へ」と、庄内産直センターの中で活動し、神奈川県保育園との産直交流にも参加した。
その中で、「私は、旧藤島町の地名を調べ『藤島歴史風土記』を2005年発行した。それにしてはお粗末であった。苗場保育園の「苗場」が目に入ってこなかったのである。」
「〝苗場〟は稲の育つ場所、保育園は人の育つ場所。それぞれが『稲と人』を育てるという共通性がある。私たちはこちらの事を知らせることに力を入れ、相手の保育について知ろうとしてこなかった。」
先生の視点はいつも、人を育てる教育者であることに納得するのである。